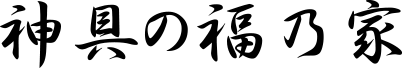神具・神祭具にまつわる豆知識
Column
-
神具・神祭具 豆知識
神具・神祭具のバリエーション
私ども福乃屋でも、多くの種類の神具・神祭具を扱っていますが、日本には本当に数多くの神具・神祭具があります。
神祭具の種類が豊富になった理由には、神道が多神教であり、八百万(やおよろず)の神々が祀られてきたことが関係しています。
それぞれの神に適した供物や儀式が存在し、時代や地域ごとに異なる神具が発展したこともその要因と思われます。
特に、日本神話にも登場する、鏡・剣・勾玉といった三種の神器のような神具は、権威や神聖性の象徴として扱われています。
さらに、稲作文化と結びついた神道の祭祀では、五穀豊穣を祈願するために多くの神祭具が用いられるようになりました。
神饌(しんせん)として米や酒、塩などを供えたり、地鎮祭や新嘗祭といった祭事の際に特定の神具が使用されるのも、この流れの一環です。
ご存じの通り、伏見稲荷大社の神様は、農業(稲作)との関連が深いですので、ここで用いられる神祭具のバリエーションが豊かなのは納得がいきます。
また、伏見稲荷大社の神様は、お祭りや賑やかに祀られることを好まれるとされています。
こちらの氏子さんをはじめ信仰心の厚い方々が多数、稲荷神に崇拝の念を持って参拝されるため、常に新しい神祭具が奉納されます。