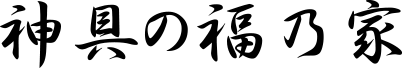幕 / のぼり / 賽銭箱にまつわる豆知識
Column
-
注連縄 豆知識
しめ縄~豆知識~
みなさんこんにちは。
以前もこのブログにおいて、しめ縄の起源などについてご紹介をさせて頂きましたが、今回もしめ縄についてお話をしていきます。
雑学として頭に入れておいて頂ければ幸いです。
まずは、しめ縄の材料・作り方です。
ある程度想像はつくと思いますが、材料は主に稲わらが使用されます。
刈り取った稲を天日干しして乾燥させます。
一旦乾燥させた稲わらを柔らかくするために水に浸し湿らせ、湿らせた状態で一定の方向に撚りながら縄状にします。
この撚りも撚る方向によって「左撚り」や「右撚り」といった違いがあり、地域や用途によって異なることがあるそうです。
装飾として「紙垂(しで)」と呼ばれる白い紙をつけたり、稲穂や橙、松葉を飾ることもあります。
しめ縄は全国各地で作られますが、特に、島根県出雲市のしめ縄作りは盛んで、職人が手作業で丁寧に作る伝統が受け継がれています。
特に出雲大社で使用される「大しめ縄」は大変有名です。
また、広島県備後地方(福山市や尾道市など)もその高い技術が評価されており全国の需要にこたえています。
また、茨城県や新潟県でも盛んにしめ縄が作られています。これは高品質な稲わらがたくさん入手できることと関連しているようです。
しめ縄には地域や神社ごとの特色があり、縄の太さや撚り方、飾りの種類が異なることもあるようです。
また、神棚に祀る際は、正月や祭礼などに合わせて新しいしめ縄に交換するのが一般的とされています。
今年の大みそかに真新しいしめ縄を飾り、新鮮な気分で新しい年をお迎えするのはいかがでしょうか?